ソーシャルワークとは?
ソーシャルワークとは、人々が生活の中で直面する困難を軽減し、社会とのつながりを活かして解決を助ける活動です。
対象となるのは
・子ども(虐待、ヤングケアラー、不登校など)
・高齢者
・障がいのある人
・生活に困っている人
など幅広く含まれます。
ソーシャルワーカーの役割は、ただ「話を聞く」だけにとどまりません。
地域の制度やサービスを紹介したり、関係者をつなぐことで、その人らしい生活を支え、QOLの向上を図ります。
具体例としては――
- 経済的に困っている家庭へ生活保護や就労支援を紹介する
- 不登校の子どもに学校や医療、家庭を結びつける調整を行う
- 高齢者が孤立しないよう、地域の見守りや介護サービスを整える
こうした実践の根底にあるのは「人の尊厳を大切にする姿勢」です。
今回は、以下の文献を参考に、「ソーシャルワーク技術」について一緒に学んでいきましょう💪
【参考文献】
ソーシャルワークの主なプロセスとは?
ソーシャルワークは、段階をふんで支援を進めるのが特徴です。
主な流れは次の7段階です。
- エンゲージメント
信頼関係を築き、安心して話してもらえる関係をつくる。 - アセスメント
生活状況や課題を整理し、どんな支援が必要かを理解する。 - プランニング
本人や家族と一緒に、支援の計画を立てる。 - インタベーション
実際に支援を行い、必要なサービスや制度につなげる。 - モニタリング
支援がうまくいっているかを定期的に確認する。 - ターミネーション
支援の終了を話し合い、次のステップに進める準備をする。 - アフターケア
支援終了後も必要に応じてフォローし、再び困らないよう見守る。
たとえば、不登校の中学生を支援する場合、最初に信頼関係を築き、学校や医療と連携を取り、復学後も見守るという流れになります。
ソーシャルワーク実践事例
1. 不登校の小学生への支援
- 事例
小学生のAくんは、学校での人間関係に不安を感じ、不登校が続いていました。母親も心配しつつ、どう接すればよいか悩んでいました。 - ソーシャルワークの実践
ソーシャルワーカーは、家庭訪問を行い、母親の気持ちを丁寧に傾聴。Aくんの思いを引き出すために、本人と安心できる場で面談を重ねました。また、学校の担任やスクールカウンセラーとも連携し、少しずつ「保健室登校」から始められる環境を整備しました。 - 効果
「休んでいても受け入れてもらえる」という安心感がAくんに芽生え、週に数回は登校できるようになりました。母親もサポート体制があることで孤立感から解放されました。
2. 障害のある方への就労支援
- 事例
発達障害をもつ20代のBさんは、職場でのコミュニケーションが苦手で、何度も仕事を辞めていました。 - ソーシャルワークの実践
就労支援センターのソーシャルワーカーは、Bさんの得意・不得意を整理し、本人に合った職種を一緒に検討。職場実習を通して「マニュアルが明確な作業」で力を発揮できることがわかりました。また、職場に対しては「業務手順を文書化する」「質問できる支援者を配置する」といった合理的配慮を提案しました。 - 効果
Bさんは継続して働ける職場を得られ、自己効力感が高まりました。企業側も「戦力になる人材」として前向きに受け入れる意識が広がりました。
3. 一人暮らし高齢者の方への支援
- 事例
独居高齢者のCさんは、体力の低下や買い物の困難から生活が不安定になり、「このまま一人で暮らせるのか」と心配していました。 - ソーシャルワークの実践
地域包括支援センターのソーシャルワーカーは、まずCさんの希望を聞き取りました。「できるだけ自宅で過ごしたい」という願いに沿い、訪問介護や宅配食サービスを導入。また、近所の見守りボランティアともつなげました。 - 効果
Cさんは安心して在宅生活を継続でき、孤独感も軽減。地域全体で支える仕組みが強化されました。
👉 このように、ソーシャルワーカーは 本人の思いを大切にしながら、周囲とのつながりを調整し、生活を支える 役割を担っています。
バイスティックのソーシャルワークの7原則とは?
ソーシャルワークには、実践の姿勢を示す「7つの原則」があります。
- 個別化:一人ひとりの事情や背景を大切にする
- 感情表出の許容:安心して気持ちを出せるようにする
- 統制された情緒的関与:冷静さを保ちながら共感的に関わる
- 受容:相手をそのまま受けとめる
- 非審判的態度:批判や裁きをしない
- 自己決定:最終的な選択は本人が行う
- 秘密保持:話したことは守る
たとえばDVを受けている女性を支援する場合、批判せずに気持ちを受け止め、安全な場所を自分で選べるよう支えます。
エンパワメントアプローチとは?
「エンパワメント」とは「力を取り戻すこと」を意味します。
支援者が一方的に助けるのではなく、本人が自分の力を発揮できるようにサポートするのが特徴です。
事例でいうと――
- 就職活動で苦労する若者が、得意なことを見つけ自信を取り戻す
- ボランティア活動で小さな成功を体験し「自分にもできる」と思える
本人が「生きる力」を自覚し、将来に向けて前向きになることがエンパワメントの狙いです。
マッピング技法とは?
マッピング技法とは、人間関係や社会資源を図にして整理する方法です。
代表的なものに エコマップ と ジェノグラム があります。
エコマップ
本人を中心に、家族や学校、医療機関、地域との関係を円や線で表します。
つながりの強弱や緊張を見える化することで、支援の方向性がわかります。
例(中学生のひきこもりケースのエコマップ):
弱い繋がりは、本来破線です。
学校 ○
│(弱いつながり)
本人 ○──○ 家族(強いつながり)
│
医療機関 ○
ジェノグラム
家系図のように家族のつながりを図示し、関係性や歴史を整理します。
例(3世代家族のジェノグラム):
祖父 □──○ 祖母
│
────┐
父 □──○ 母
│
子ども ○
こうした図を一緒に見ることで、本人も自分の状況を客観的に理解できます。
アウトリーチとは?
アウトリーチとは、困っていても自分から相談に来られない人のもとへ支援者が出向くことです。
具体例として――
- 地域で孤立している高齢者を家庭訪問する
- ホームレス状態の人へ声をかけ、支援につなぐ
- 虐待が疑われる家庭を訪ね、子どもの安全を確認する
ただ訪問するのではなく、信頼を築きながら必要な支援や制度を紹介していく姿勢が求められます。
アドボカシーとは?
「アドボカシー」とは「代弁」や「権利擁護」を意味します。
声を上げられない人や、不利益を受けやすい人の立場を守るために、代わりに声を届ける活動です。
具体例として――
- 障がいのある子どもが学校で合理的配慮を受けられるように働きかける
- 生活困窮者が制度の申請を拒まれたときに同行しサポートする
- 虐待を受けている子どもに代わって、安全な環境を求める声を届ける
重要なのは「本人の意思を尊重しながら、一緒に声を届ける」という姿勢です。
アドボカシーの類型
- セルフアドボカシー:本人が自分の思いを自分で表現できるように支援する。
- リーガルアドボカシー:法的な手段を使って権利擁護を行う(例:弁護士との連携)。
- コーズアドボカシー:社会的な課題について、制度の改革や社会資源の開発、福祉文化の創造などに働きかけて、変革を目指す。
- ケースアドボカシー:個人や家族などの権利を擁護するためのアドボカシー
- クラスアドボカシー:特定のニーズをもつ集団の権利を擁護するためのアドボカシー
- 市民アドボカシー:地域住民が連携し、弱い立場にいる人々の権利を代弁する。
これらを使い分けることで、個人から社会全体まで幅広い支援が可能になります。
ソーシャルワーク専門職のグローバル定義とは?
国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)は、ソーシャルワークを次のように定義しています。
- 人々の 生活向上と社会変革 をめざす
- 人権と社会正義 を大切にする
- 専門的な知識・理論・倫理に基づいて実践する
つまりソーシャルワークは「困っている人を助ける」だけでなく、「社会をより良く変えていく」役割も担っています。
まとめ
ソーシャルワーク技術とは、人と社会をつなぎ「その人らしい生き方」を支えるための専門的な方法です。
- 7段階のプロセスで丁寧に支援を進める
- バイスティックの7原則に沿って人の尊厳を守る
- エンパワメントで本人の力を引き出す
- マッピングで関係を可視化し、支援につなげる
- アウトリーチで声を届けられない人のもとへ行く
- アドボカシーで権利を守り、声を届ける
- グローバル定義にあるように、人権と社会正義を実現する
こうした技術や姿勢を通して、ソーシャルワーカーは人と社会を結ぶ架け橋となります。
【参考文献】
最後までお読みいただき、ありがとうございました✨
いつも、記事を読んでくださり本当にありがとうございます。
スキ・フォローとても励みになっています🍀
この記事を読まれた方が、
少しでも『ソーシャルワーク技術』について興味を深めていただき、
少しでも参考になれば嬉しいです🌈
今後もできる限り有益な記事を書いていきますので
よろしくお願いします。
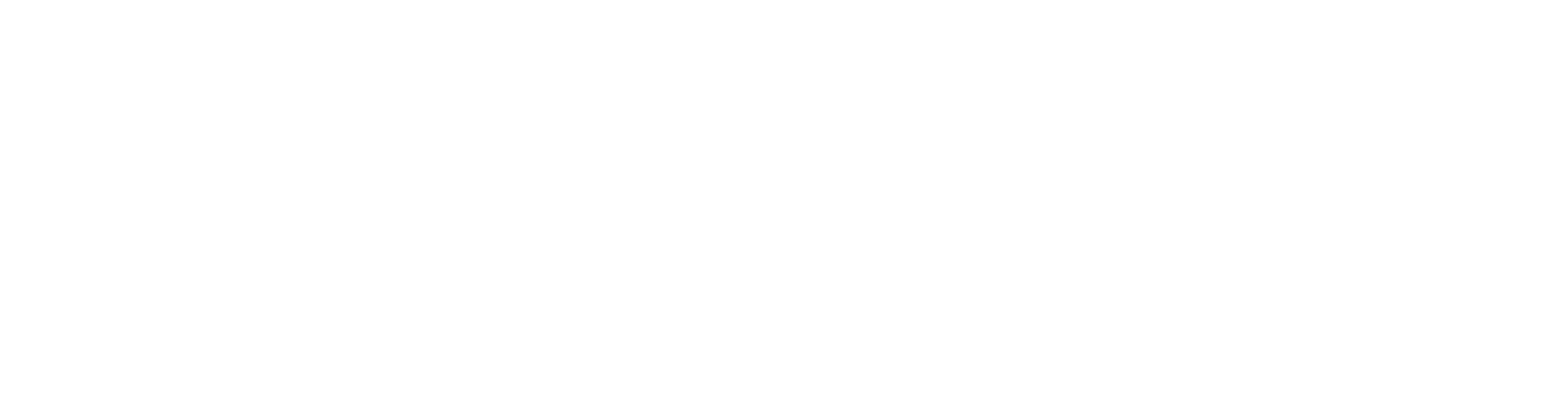



コメント