ソーシャルワークとは?
ソーシャルワークとは、生活の中で困りごとを抱える人を支える専門的な支援のことです。
思春期・青年期の子どもたちは、家庭や学校、友だち関係など、いろいろな場面でつまずきやすい時期です。
家族の問題、学校でのトラブル、将来への不安など、一人で抱えるには大きすぎる悩みを持つ子も少なくありません。
そんなとき、ソーシャルワーカーは
- 子ども本人の気持ちに寄り添う
- 家族と一緒に考える
- 学校や地域の機関とつなぐ
- 社会の制度やサービスを上手に活かす
など、いろいろな形で子どもを支えます。
子どもが「自分らしく安心して生きていける」ように、周りの大人と協力してサポートしていくのがソーシャルワークです。
今回は、以下の文献を参考に、ソーシャルワークについて一緒に学んでいきましょう💪
【参考文献】
本人への関わり方
思春期・青年期の子どもたちは、心も体も大きく変化し、不安定になりやすいのが特徴です。
友だち関係や勉強、家族とのすれ違いなど、ちょっとしたことが大きなストレスになります。
ソーシャルワーカーは、まず「安心して話せる関係づくり」を一番大切にします。
- どんな話でも「うんうん」と聞く
- 気持ちを言葉にできるまで待つ
- 「わかってくれる人がいる」と思ってもらう
こんな関わりを心がけています。
思春期・青年期には、心が不安定になることで、いろいろな行動が出ることがあります。
例えば、
- 暴言・暴力
- 子ども帰り(退行)
- 反抗的な態度
- お試し行動(わざと困らせて、愛情を確かめる)
- 自傷行為(リストカットなど)
こうした行動は「わかってほしい」「安心したい」というサインです。
対応するときは、
- 頭ごなしに叱らず、気持ちを受け止める
- 「何がイヤだった?」「どこがつらかった?」と聞いてみる
- 落ち着く時間と場所を用意する
- 危険なときは安全を最優先にする
- 退行は責めず、甘えを一度受け止める
- お試し行動に振り回されず、大人がブレないようにする
などが大切です。
そして、子どもの気持ちに寄り添う中で大事なのが「逆転移」と「陰性感情」に気づくことです。
子どもの強い感情に触れていると、大人自身もイライラしたり感情的になったりすることがあります。
相手の感情に引き込まれることを逆転移と言い、「嫌だな」と思ってしまう気持ちは陰性感情と呼ばれます。
私も数年前に関係性が上手くいかなかった児童に対して困ることがあり、今思い返すとその子に陰性感情を抱いていたんだと今さら自覚します💦
これらは誰でも抱く自然な感情だと思います…
大事なのは、
- 自分の感情に気づいて整理する
- 一人で抱え込まず、同僚やスーパーバイザーに相談する
- 感情的になりそうなら、距離をとって冷静になる
ことです。
大人が安定していることで、子どもも安心できます。
必要に応じて、
- カウンセリング的な関わり
- 学校や先生との調整
- 医療機関や専門機関の紹介
なども行います。
子どものペースを大切に、小さな「できた!」を一緒に増やしていくことが自立のための力に繋がると考えています🍀
家族への関わり方
子どもの支援は、家族の協力なしでは十分にできません。
だから、ソーシャルワーカーは子どもだけでなく、家族にも寄り添います。
- 保護者と一緒に子どもの困りごとを整理する
- 家庭でできるサポートを考える
- 保護者の悩みや不安を聞く
- きょうだい児の気持ちにも目を向ける
家庭の中で誰か一人が無理をしないよう、みんなで支え合える形を一緒に探します。
必要に応じて、
- 家族の役割分担を見直す
- ストレスを減らす方法を一緒に考える
ことも大切です。
虐待やDVなど深刻な問題がある場合は、行政機関や専門機関と連携し、子どもの安全を最優先に行動します。
「相談してもいいんだ」と思える場所があるだけでも、家族の気持ちは少し軽くなります。
関係機関との関わり方
思春期・青年期の支援は、一人だけではできません。
学校、医療機関、児童相談所、地域の支援センターなど、さまざまな関係機関とチームで取り組みます。
ソーシャルワーカーは、そのつなぎ役を担います。
- 学校の先生やスクールカウンセラーと情報を共有する
- 学校での学習面・生活面のサポートを整える
- 医療機関と連携し、治療や診断に沿った支援を考える
- 児童相談所、地域のNPO、子ども支援センターなどを活用する
バラバラにならないように、
- 定期的にケース会議を開く
- 支援の方針をみんなで共有する
ことが大切です。
「どこに相談しても同じ方向で支えてもらえる」という安心感をつくります。
自立へ向けた支援
思春期・青年期の子どもにとって、自立は大きなテーマです。
でも、いきなり一人で全部できるようになるわけではありません。
だからこそ、段階的に準備を進めることが大切です。
- 得意なことや好きなことを見つける
- 小さな成功体験を積み重ねて自信をつける
- アルバイトやボランティアで地域とつながる
- 就労支援や若者サポートステーションを活用する
- 進学・就職、一人暮らしなどを一緒に計画する
- 奨学金などの制度を紹介して手続きをサポートする
- 必要に応じてグループホームを利用して安心できる居場所をつくる
- 同じ立場の仲間とつながる自助グループへ参加する機会をつくる
「困ったときは相談していい」という安心感と、「自分で一歩踏み出せた」という経験を増やすことが大切です。
経済的な支援方法
経済的な理由で進学や生活をあきらめる子がいます。
そんなとき、ソーシャルワーカーは一緒に経済的なサポートを考えます。
- 奨学金の情報を伝え、申請を手伝う
- 生活保護や児童扶養手当などの公的制度を活用する
- ひとり親家庭や低所得世帯向けの支援金を紹介する
- 学用品や給食費の援助など学校の制度を活用する
- グループホームや家賃補助などを活用する
- 必要に応じて地域のNPOやボランティア団体を紹介する
お金のことは一人で抱え込むとつらくなります。
だからこそ、「一緒に調べてみよう」「できる方法を探そう」と寄り添いながら、使える制度をつなぎます。
最後に
思春期・青年期の子どもたちは、たくさんの可能性を秘めています。
でも、ときには大きな壁にぶつかり、立ち止まることもあります。
そんなときに「一人じゃないよ」と伝えるのが、ソーシャルワーカーの役割です。
- 子どもの声を聴く
- 家族と一緒に悩む
- 学校や地域と手を組む
- 必要な制度を届ける
こうした積み重ねが、子どもたちの安心と自信を育てます。
私は、ソーシャルワーカーではありませんが、子どもに関わる支援者として、これからも子どもたちが自分らしく歩めるように、そばで一緒に考えていきたいと思っています。
【参考文献】
最後までお読みいただき、ありがとうございました✨
いつも、記事を読んでくださり本当にありがとうございます。
スキ・フォローとても励みになっています🍀
この記事を読まれた方が、
少しでも『ソーシャルワーク』について興味を深めていただき、
少しでも参考になれば嬉しいです🌈
今後もできる限り有益な記事を書いていきますので
よろしくお願いします。
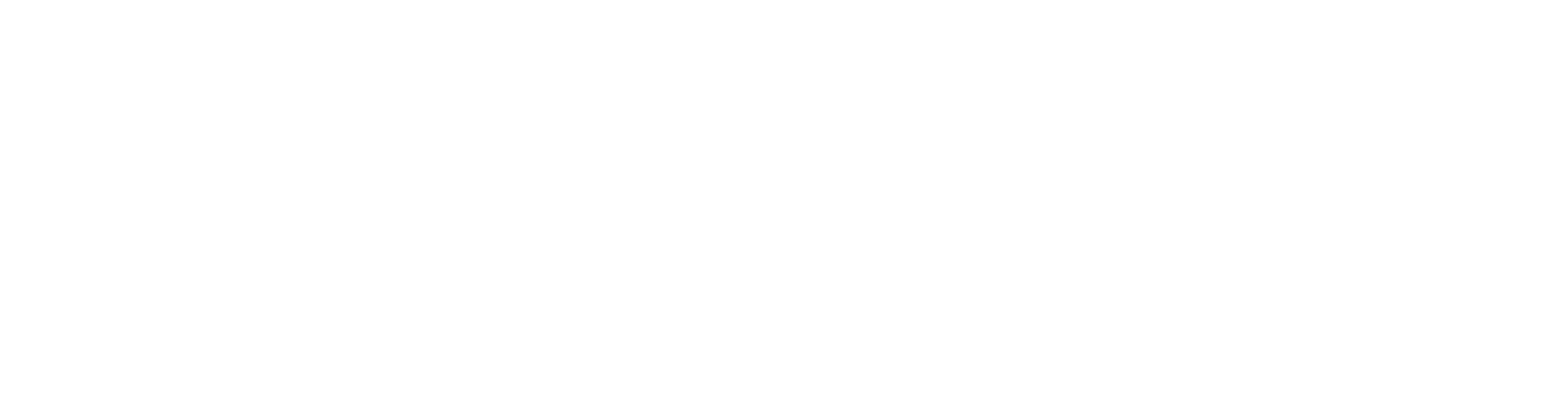



コメント