〜2025年8月25日 発売〜
こんにちは。今日はうれしい(私が)ご報告です。
私の初めてのKindle本、『交錯する!? 発達と愛着の障害』 がいよいよ発売させていただきます📗
明日から無料キャンペーンを実施する予定です🌟
これまでnoteでたくさん書いてきた記事をベースにしながら、
新しい事例や図解を加えて、
「1冊まるごとで読める学びのガイド」にまとめました。
リンク
どんな本なの?
内容は、発達障害と愛着障害の“交錯する部分”をわかりやすく整理し、
事例や実践方法とともに紹介しています。
章ごとの流れを、ざっくりご紹介します👇
第1章 発達と愛着 ― 似ているようでまったく違う
- 発達障害と愛着障害の基礎
- 「似ているようでちがう」そのポイント
- 事例:注意されがちな小4男子Aくん
- 事例:関係づくりが難しい小5女子Bさん
- 区別がなぜ難しいのか? → 最初の一歩を考える
第2章 「どちらか」ではなく「どちらも」
- 両方が重なり合うケース
- 事例紹介(2パターン)
- 支援が難しくなる理由
- 突破口や実践例
- 保護者・先生が陥りやすい“落とし穴”
第3章 チームで支えるために
- どうして「連携」が大事なのか?
- 連携を阻む3つの壁
- 実践ステップ①〜⑤
- 信頼関係を守る心得
第4章 家庭での工夫
- 安心感をどうつくる?
- 「構造化」の大切さ
- 事例:小学生Aちゃん・Bくん
- 安心感と構造化を両立させるコツ
- 親の心構え
第5章 学校での工夫
- 学校での安心感づくりの3つの柱
- 事例:Cくん(小2)、Dさん(中1)
- 学校でできる構造化の工夫
- 教師の心構え
第6章 思春期の壁と変化
- 思春期に特有の課題
- 自己肯定感をどう支える?
- 事例:Eくん(高1)、Fさん(中3)
- 大人が気をつけたいこと
第7章 支援者自身を守る
- 「支援者も人間」だからこそ
- 燃え尽きサインとセルフケア
- 事例:G先生(小学校教師)
- 保護者の工夫/チームで支える力
第8章 子どもたちの声に耳を傾ける
- 4つの事例紹介
- 共通して見えるものを整理
- まとめ
終章
本を通じて伝えたいメッセージを、やさしくまとめています。
最後に
『交錯する!? 発達と愛着の障害』は、
私がこれまで現場で見てきたこと、
そしてnoteで発信してきたことの集大成です。
📗 2025年8月25日、Kindleストアで発売開始
少しでも
子どもたちや
子どものサポーターたち
のお役に立てると嬉しいです🌟
リンク
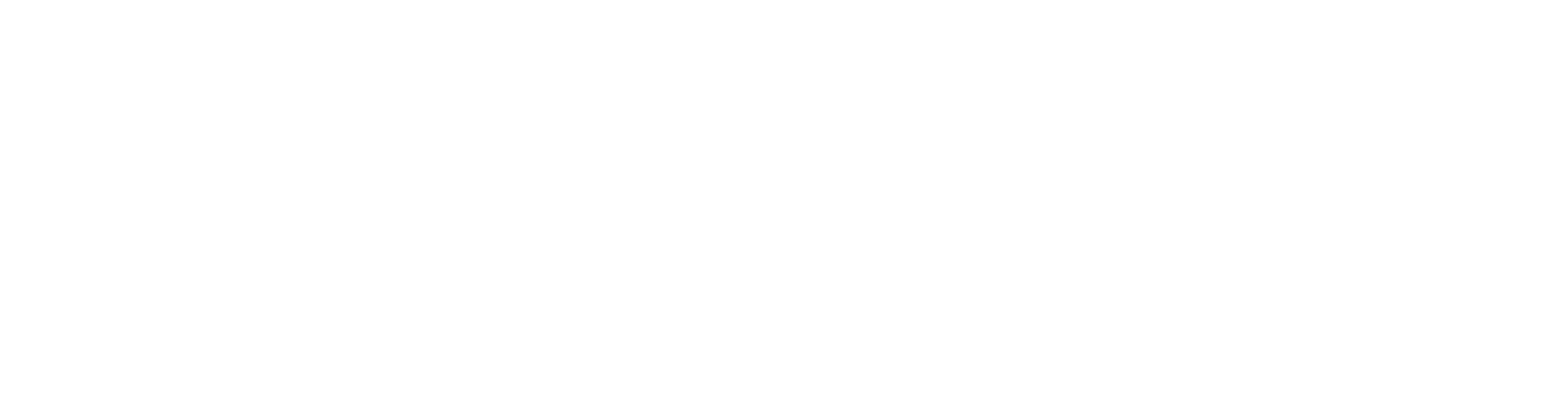



コメント