収入の7割で暮らす!
家計を整えるときに大事なのは、「使いすぎない仕組み」を先につくること。
わたしンチでは、「収入の7割で暮らす」を合言葉にしています。
たとえば、世帯の手取り年収が600万円なら
- 支出は420万円以内
- 残りの180万円は貯金や投資にまわす
- 600万円の内、180万円の収入はないものと考える。
「ここまでしか使わない」と上限を決めておくことで、自然とお金の使い方が整っていきます。
理想は、毎月、収入の7割で暮らすことですが
夏休みなど家族旅行に出かけることもあり
どうしても、月収の7割で暮らすのは難しいです。
わたしンチでは、少し緩く、
12月終了時点で、支出が年収の7割に収まるように予算計画をたてています。
ポイントは、「固定費を減らすこと」。
毎月の支出の中で見直しやすいのは次の3つです。
- 住宅ローン(ネット銀行に借り換え済)
- 保険料(必要保障額:わたしんチは『収入保障保険』)
- 通信費(スマホは格安プランへの切り替え(日本通信)&マネーフォワード光)
さらに、サブスクや自動更新のサービスも意外と大きな出費。
「なんとなく続けているもの」を一度見直すことも大切です。
7割で暮らす習慣がつくと、貯金は自然に増えはじめます💰↑
ただし7割は、現在子が小学生✖️2なので実現できていることだと思います。
子が高校生、大学生となると、どうしても出費は増えます
かかりどきの時は、収入の9〜10割、場合によっては11割(マイナス家計)で暮らす目標にチェンジする予定です。
貯めどきの今こそ、7割生活を定着させ、将来に備えたいと考えています💰
逆に、収入の7割は使う!
お金は「使ってこそ生きる」もの。
どうしても、節約のことばかり考えていると、今を楽しむことが難しくなってしまいます💧
7割で暮らすとはいえ、
その7割はしっかり使う(3割以上貯めない)と決めています🔥
支出には大きく2つの使い方があります。
- 消費:生活に必要な食費、光熱費、住居費など
- 浪費:家族の幸せや成長につながる使い方
- 死んだお金:惰性で払っているムダな支出(基本0を目指す)
たとえば
- 家族旅行や外食など、笑顔を生む支出
- 健康・教育・学びへの投資
- 家の快適さを上げる工夫
こうしたお金は「生きたお金」です。
反対に、「なんとなく買ったお菓子」や「放置しているサブスク」は、見直すチャンス。
節約の目的は「幸せを減らすこと」ではなく、「ムダを減らすこと」です。
同じ7割でも、使い方次第で生活の満足度は大きく変わります。
7割の中で、固定費は極限まで削ります。
そして、7割のうちの浮いた予算は浪費に回します🍀
浪費といっても、自分にとって、家族にとって満足度の高いもの
(旅行、キャンプ、外食、趣味etc)
は何か、吟味した上で思い切って使っています。
趣味のものを買うとき(ギター、自転車、ゲーム、本など)
は、必ずリセール(売ろうと思った時にどの程度の価値があるか)を考えた上で購入するようにしています。新品には拘らず、自分にとって満足度が高ければOK💰
お金から自分にとっての価値を引き出す力って
奥が深いなぁと常々感じます🍀
わたしンチのポートフォリオ💰残り3割は投資と貯金
「貯める」と「増やす」を上手に組み合わせるのが、わたしンチ流。
生活防衛資金(生活費の1年分)以外は、運用しています。
ポートフォリオ(金融資産の大よその内訳)
- 投資(60%):NISA・iDeCoなどを活用
- 個人向け国債(20%):5〜10数年以内に使う教育費や車検費用
- 現預金など(20%):生活費+控金(暴落時の投資資金)+生活防衛資金(生活費の半年〜1年分)←有事の時以外手をつけない。
教育資金として「個人向け国債」に投資
教育資金の一部は、個人向け国債(変動10年)にしています。
理由はとてもシンプルです。
安全性が高く、途中解約しても元本が守られるからです。(過去2回分の利息は返金する必要がありますが…)
たとえば
- 「5年後の高校入学金」など、使う時期が決まっているお金
- 株式投資のようなリスクは取れないお金(使うときが決まっているので、その時暴落していたら困る)
- たちまち使う予定はないので、預金より少しでも利息を得たいお金
そんな目的にぴったりなのが、個人向け国債です。
(現在の利率は1%ほどで、普通預金の3〜4倍)
教育資金は「増やすお金」と「守るお金」を分けておくのが安心。
リスクを取らない部分を国債で運用することで、心にもゆとりが生まれます。
NISA積立枠は夫婦でフル活用
2024年から始まった新NISAは、家庭の味方です。
わたしンチでは、夫婦それぞれのNISA口座で積立をしています。
- 一人あたり年間120万円まで非課税で投資
- 夫婦で合わせると年間240万円の非課税枠
投資信託を毎月自動で積み立てる「つみたて投資」が基本です。
おすすめは、手数料が低いインデックス型ファンド。
たとえば
- 全世界株式インデックス
- S&P500連動インデックス
世界全体やアメリカ市場に分散することで、安定的な成長を狙います。
ポイントは「長期で放っておくこと」(気絶投資😵)
時間が味方になって、いつのまにか大きく育っていきます。
暴落時にNISA成長投資枠に追加
投資をしていると、必ずやってくるのが「暴落」。
暴落=チャンス」と考えます。
普段は積立だけですが、市場が大きく下がったときは追加投資を実行。
ルールはあらかじめ決めておきます。
- 株価が〇%下がったら、成長投資枠で追加購入
- 生活費には手をつけない
- 余裕資金だけを使う
こうしておくと、「怖くて動けない」という心理に流されません。
そのため、預金のうち数%はいつでも投資できる控え金(ベンチメンバー)として、手元に置いています。
暴落時の追加投資は、将来のリターンを大きくするカギです。
そのためにも、全力投資をせず、日ごろから現金を少し残しておくのがポイントです。
1月に予算計画
わたしンチでは、毎年1月に「家計会議」を開きます。
コーヒーを飲みながら、家族でゆるっと話し合う時間です☕️
- 去年、何にどれだけお金を使った?
- 今年はどんなことにお金をかけたい?
- 旅行はどこに行きたい?
- 教育費、習い事の費用は?
- 家のメンテナンスは?
- そろそろ壊れそうな家電は?
こうして、1年の「お金の地図」を描いておきます。
大きな分類としては、
1.消費 (食費、光熱費など)⇦ 最適化
2.特別費(家電の故障や、冠婚葬祭などに備えて、年50万ほど)
3.浪費 (心を豊かにするための出費)⇦ 予算内で最大化
「使う目的」を決めておくことを大事に予算計画を立てています💰
お金に色はありませんが、目的を与えたとき、最大限の力を発揮してくれる
そんな気がしています💰🔥
年間の予算を立てておくと、使うときの罪悪感もなくなり
「今を楽しむ」ことと、「未来に残す」ことのバランスがとりやすくなります。
お小遣いは年間計算
夫婦のお小遣いは、月単位ではなく「年間」で管理しています。
たとえば、年間40万円なら
- 月あたりの目安は3万円ちょい
- まとめて使っても、トータルで収まればOK
この方法だと、「今月足りない!」ということが減り
季節ごとの支出にも柔軟に対応できます。
たとえば
- 春:新しいスーツや靴を購入
- 夏:趣味のグッズ購入やイベント参加
- 秋冬:控えめに過ごしてバランス調整
また、家族で「お小遣いルール」を共有しておくとトラブル防止にも◎。
予算内であれば、何に使っていても、互いに干渉はしないようにしています!
小学生の子どもには、年間管理はまだ難しいので、週ごとや月毎のお小遣いにしています。
「自分で考えて予算の中でやりくりする」体験をさせるために
使い方については、あれこれ口出しはしません。
相談には乗ります。
大人が見せるお金の使い方が、最高の金銭教育になると信じています✨
まとめ
家計管理のコツは、「バランス」と「習慣」。
節約だけでも、浪費だけでも、どちらも長続きしません💧
わたしンチでは、次のルールを軸にしています。
- 収入の7割で暮らす
- 残り3割で未来をつくる
- NISA(投資信託・株)と国債でリスク分散
- 暴落時はチャンスを逃さない
- 年初に予算を立てて家族会議
- お小遣いは年間で管理
家計とは、単なるお金の出入りではなく「人生設計の一部」です
数字の管理を超えて、「どんな暮らしをしたいか」を描くことが大切を大切にしています。
収入の7割で「今を楽しみ」、3割で「未来をつくる」。
わたしンチの家計管理は、今日もその真ん中で、ちょうどいい暮らしを続けています🍀
最後までお読みいただき、ありがとうございました✨
いつも、記事を読んでくださり本当にありがとうございます🍀
この記事を読まれた方が、
少しでも『家計管理』について興味を深めていただき、
少しでも参考になれば嬉しいです🌈
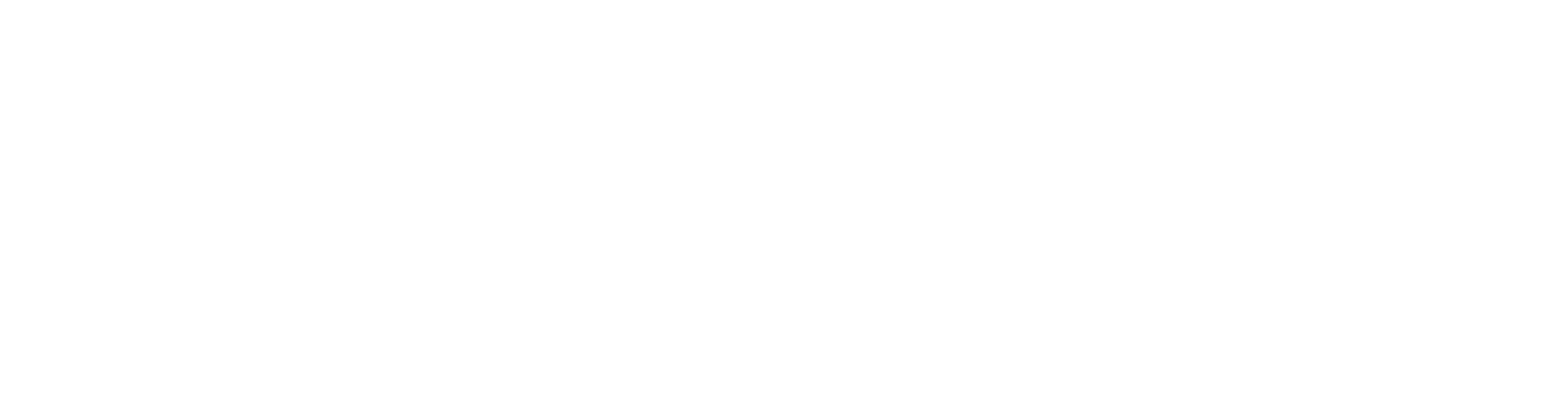



コメント