子どもが突然キレて大声を出したり、物を投げたりすると、びっくりしますよね。
「どうしてこんなに怒るの?」
と困ってしまうことも多いのではないでしょうか。
私も、小学校教員時代、大人からすればほんの些細なことでキレる子への対応に疲弊してしまうことがありました。
今回は精神科医の原田謙Dr.が著書の以下の文献を参考に、キレる子どもの気持ちや、接し方について、一緒に考えていきましょう💪
【参考文献】
怒るとキレるの違いとは?
「怒る」と「キレる」は、似ているようで実は違います。
「怒る」とは、嫌なことがあったときに気持ちを表す自然な行動です。
「怒る」という気持ち自体は、決して悪いことではなく、むしろ人間として自然な感情です。
一方で「キレる」は、怒りが爆発して自分でも止められなくなり、不適切な行動化が見られる状態です。
キレると、こんな行動が出やすくなります。
- 物を投げる
- 大声で叫ぶ
- 人を叩く、蹴る
- 暴言を吐く
怒ること自体は大切な自己表現です。
でもキレてしまうと、周囲を不快にさせるばかりか、本人も後でつらい気持ちを抱えがちです。
どうしてキレるの?
子どもがキレる理由を知っておくと、大人も少し気持ちが楽になります。
主な理由は次のようなものがあります。
- 感情のコントロールが未熟
→ 小さい子どもほど、気持ちを言葉で伝えるのが難しいです。 - 安心できる場所がないと感じている
→ 家庭や学校で「わかってもらえない」と思うと、爆発しやすくなります。 - 隠れたストレスがたまっている
→ 勉強、友達関係、家庭の事情など、大人が思っている以上に繊細です。 - 不当性を感じている
→ 自分だけが理不尽に怒られたり、不公平に扱われたと感じると怒りが爆発します。 - 故意性を感じている
→ 誰かにわざと嫌なことをされたと感じると、我慢できず一気に感情が噴き出します。
キレる裏には、「わかってほしい」という強い気持ちが隠れています。
暴言・暴力の止め方とは?
暴言や暴力が出たとき、つい大声で叱りたくなりますが、まずは落ち着いて危険を避けることが大切です。
止め方のポイントはこちらです。
- 危ないものや人を遠ざける
- 短く「やめよう」とだけ伝える
- 感情的に責めず、まずは行動を止めることを優先する
- 落ち着いた後で「どんな気持ちだった?」と話を聞く
落ち着かせる方法として、
- クールダウン
→ 静かな場所に移動して一人になる時間を作ります。 - タイムアウト
→ 一定時間だけ、刺激の少ない場所で休ませます。 - タイムイン
→ できるだけ第三者がそばに寄り添い、安心できる時間をつくります。
→ 落ち着くまではキレたことを問い詰めず、気持ちが静まるのを待ちましょう。
状況や子どもの性格に合わせて、合う方法を試してみてください。
褒めるときの「25%ルール」とは?
「褒めるところがない」と悩む大人はとても多いです。
そんなときに役立つのが「25%ルール」です。
完璧じゃなくても、できたところを褒める方法です。
例えば…
- 宿題を全部終わらなくても、机に向かっただけでOK
- 5分だけでも手伝えたらOK
- 「やろうと思っただけでもえらい」と声をかける
大事なのは、小さなできたを見つけて褒めることです。
小さな積み重ねが子どもの自己肯定感を育て、キレにくい心の土台になります。
そして、支援する大人自身も「25%ルール」で自分を認めましょう。
「今日は少し冷静に対応できたな」と思えたら、それで十分です。
キレる子どもへの叱り方とは?
キレる子どもを叱るときは、大人が冷静でいることが大切です。
感情的になると逆効果になることが多いです。
叱り方のポイント
- 人格を責めず、行動だけを伝える
例)「物を投げるのはやめよう」 - 代わりの方法を一緒に考える
例)「怒ったときは深呼吸してから話そうね」 - 叱るタイミングは落ち着いてから
- 何度も同じことを言わず、短く具体的に
叱った後は、できれば良かったところも一つ伝えてあげましょう。
「今日は途中で話を聞けたのはえらかったね」と伝えるだけで、子どもの安心感が変わります。
相談できる場所とは?
「もう一人では限界かも」と思ったら、迷わず誰かに相談してください。
相談できる場所はたくさんあります。
- 学校の先生
- スクールカウンセラー
- 児童相談所
- 子育て支援センター
- 児童精神科、小児科などの医療機関
誰に相談したらいいか迷ったときは、まず学校の先生に相談されると良いかも知れません。
学校では教育相談日として、
・スクールカウンセラー
・スクールソーシャルワーカー
・特別支援教育コーディネーター
・養護教諭
・学級担任
などに相談できる日が設定されていることが多いです。
一人で抱え込むと、大人の心もすり減ってしまいます。
話すだけでも気持ちが整理されます。
最後に
キレる子どもに向き合うのは、大人にとっても大きなエネルギーが必要です。
でも、子どもの心には「わかってほしい」という思いがちゃんと隠れています。
完璧な対応は必要ありません。
- 少しでも落ち着いて関わる
- 小さなできたを見つけて一緒に喜ぶ
「一緒に成長していこう」という気持ちで、子どもの困り感に寄り添うことが大切だと考えています🍀
【参考文献】
最後までお読みいただき、ありがとうございました✨
いつも、記事を読んでくださり本当にありがとうございます。
スキ・フォローとても励みになっています🍀
この記事を読まれた方が、
少しでも『キレる子どもの気持ちと接し方』について理解を深めていただき、
少しでも参考になれば嬉しいです🌈
今後もできる限り有益な記事を書いていきますので
よろしくお願いします。
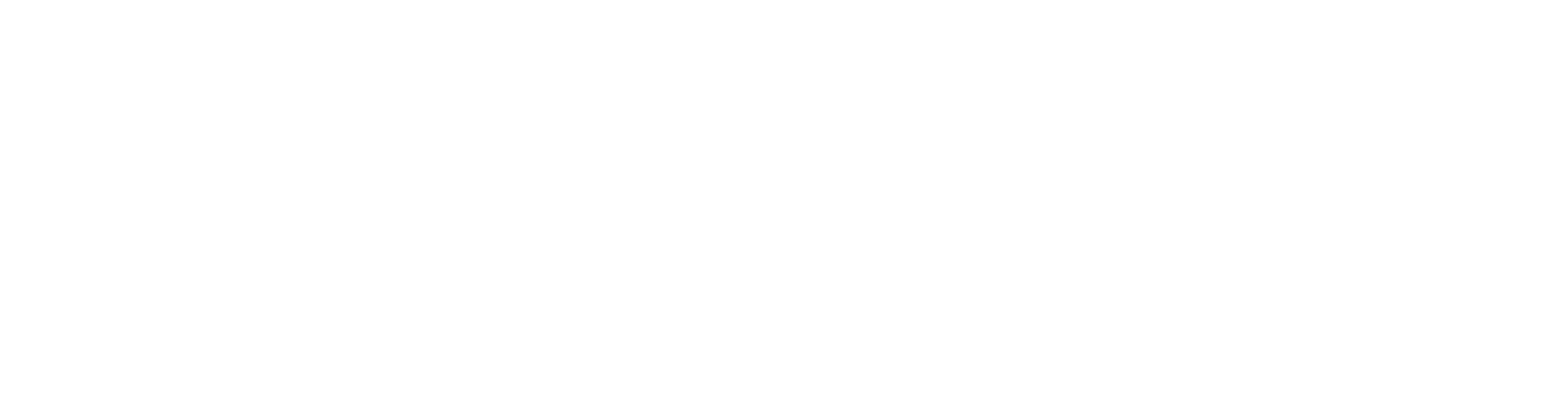



コメント