人と接する中で、

一緒にいると、ちょっと疲れるな…

何だか居心地が悪いな…
と感じたことはありませんか?
私はよくあります😅
そこで、以下の文献を手に取り、人との適切な距離の保ち方について少し学びました。
教育現場でも、同僚教師、後輩・先輩教師との距離感で疲弊してしまっている人がたくさんいます…
また児童生徒と、適切な距離を取ることができず、
近すぎたり
遠すぎたり
する関係になっていることもあります。
他人と無理して付き合うのではなく、
「こんな時、どう対応するのが望ましいのか」という切り口から
自分が心地よくいられる関係の築き方について、一緒に学んでいきましょう✏️
【参考文献】
「私の方が上!」 マウンティングされる…
職場やママ友の集まりなどで、さりげなく見下されるような発言にモヤっとすることがあります。
これは「マウンティング」と呼ばれる、優位性を示そうとする行動の一種です。
人間に限らず、他の動物でもみられる行動です…
マウンティングに巻き込まれないためのコツは以下の通りです。
無理に張り合わず「へぇ、すごいですね」と流す
内心で「この人は不安なのかも」と客観視する
頻繁に会わなければならない相手なら、物理的距離をとる
自分を守る“心のフェンス”を意識して会話する
自己肯定感を高めて、相手の言動に左右されにくくなる
マウンティングの対象となるのは、
自分と年収や経歴、実績、地位などが近い関係にある人です。
自分と明らかに、離れた存在の人には、マウンティングをとっても、
相手にダメージを与えられず、
自分も優越感に浸ることができないため
意味がないからです。
相手がマウンティングをとってくると、
ついイラッ💢としますが
感情を乱してしまっては相手の思う壺です…
「相手は自分をライバル視している証拠だ」
「同等レベルの他人と比較するなんて、残念な人だな〜」
と心の中で距離を置くことで、
マウンティングされても、心が動きにくくなります🍀
相手を変えようと思わない
「もっと優しくしてくれればいいのに」
「なんで気づかないの?」
と感じることはありませんか?
けれど、他人は思い通りに変えることはできません…
しかし、自分は変えられます💓
自分の認知を見直し、言動を変えることにより
結果的に、相手の言動も少し変わってくることはよくあります🍀
人間関係で疲れないためのポイントは以下の通りです。
「相手を変える」より「自分の関わり方を見直す」
感情を相手に委ねず、自分で整える習慣をつける
相手の性格や癖に“期待しない”ことで落ち着ける
相手の言動は「そういうもの」と割り切って受け流す
言いたいことがあるときは「私はこう感じる」と伝える
悪口大会に参加させられる…
ランチの時間や職場の休憩室で、誰かの陰口が始まることがあります。
最初はうなずくだけのつもりが、次第に自分も巻き込まれてしまうことも。
そんな場面での対応策をいくつか紹介します。
あえて話題に乗らず、表情だけでやんわり距離を取る
「否定」も「肯定」もしない
その場を離れる口実を持っておく(「電話してくるね」など)
「私はあまりその人を知らないので」と曖昧に返す
自分の意見を押し通すのではなく、中立の姿勢を意識する
距離感の合わない相手とは関係性を“浅く長く”保つのも手
悪口は、巡り巡って、自分に返ってきます…
私は、「他人の悪口を言わない」と強く心に決めています。
比較的、悪口の対象になることも、個人的には少ないと感じています。
なぜなら、悪口の標的となりやすいのは
がんばらない めんどくさくない 人間関係を築くコツ
なんといっても、いつも悪口を言っている人だからです。
自慢話に付き合わされる…
誰かの成功話や自慢話に、何度もつきあわされるのは正直つらいもの。
相手は満足していても、聞いている側にはストレスがたまります。
こうした相手とのつき合い方のヒントは以下の通りです。
話半分に聞きながら「そうなんですね」と相づちを打つ
必ずしも共感する必要はないと割り切る
無理に自分の話を合わせようとしない
「それより最近どうですか?」と話題を切り替えてみる
頻度を減らして会うことで、心の負担を軽くする
自慢話が好きな人は、
話を聞いてくれる人のところへ寄ってきます…
『必要なウソ』をついてその人と離れる
ことで、自分の心や時間を守ることが大切です🍀
クレームへの対応のコツ
理不尽なクレームや強い口調での指摘を受けると、誰でもストレスを感じてしまいます。
しかし、冷静に対応するスキルを持つことで、自分を守ることができます。
クレーム対応で疲弊しないためのコツを紹介します。
最初に「ご不便をおかけして申し訳ありません」と受け止める
相手の感情と要望を切り分けて冷静に聴く
オウム返しで共有する「〇〇でお困りなんですね。」
自分が悪くないときも、防御的にならず事実を伝える
長時間の対応は避け、必要なら上司や第三者に引き継ぐ
終わったら深呼吸や小休止を入れて心をリセットする
小学校教員時代、保護者の方からクレームを受けることがありました…
もちろん、私が不甲斐ない面もありましたが、若い頃とても傷ついてしまった経験があります…
クレーム側のペースに乗って、ただただ謝る…
そしてさらに、罵倒される…
完全に相手ペース…
昔の私のような対応では、自分も疲弊してしまいます…
経験を重ねるごとに、保護者の感情と、要望を切り分けて冷静に対応することができるようになってきました。
丁寧に接しつつ
余裕感を醸し出し
冷徹に感情と要件を切りなはして聞く
ことで、相手のペースに巻き込まれずに、自分の言い分を適切に伝えやすくなると信じています🍀
上司からの無茶振りを上手く断れない…
「とりあえずやってみて」
と突然無理な仕事を任されて困った経験はありませんか?
断れずに抱え込みすぎると、心身ともにすり減ってしまいます。
うまく距離を取るためのヒントを紹介します。
まずは「確認して対応します」と一度受け止める
無理な点を具体的に整理し、代替案を提示する
自分の状況(他の業務の優先度など)を可視化する
感情ではなく「事実」で断る姿勢を大切にする
日頃から小さな報連相を積み重ねて信頼関係を築く
「現在、Aの仕事をしており、一週間後までにBの企画準備があるので、一週間後以降なら、対応可能です。」
のように、自分のタスクと優先度を明確にしておくことで、
仕事が今は受け持てないことの根拠を示しながら断ることができます。
断るのは勇気が必要ですが、
根拠をいつでも示せるようなタスク管理をしておくことが
断る上でも大切だと考えています✏️
部下に気をつかいすぎて、指導が上手くできない…
「嫌われたくない」
「自信を失わせたくない」
と思うあまり、
必要なフィードバックを避けてしまうことはありませんか?
気をつかいすぎずに、健全な距離を保つコツは以下の通りです。
まずは「相手の成長を願っている」ことを伝える
行動や事実にフォーカスし、人格を否定しない
改善点だけでなく、できている点も同時に伝える
1対1の対話を大切にし、安心感のある関係を築く
指導=支配ではなく「伴走」の姿勢で関わる意識を持つ
ぼーっとする時間を大切に
人との距離感に悩みやすい人は、周囲に気を配る傾向が強いものです。
気づかないうちにストレスが蓄積し、疲れがたまりやすくなります。
そんなときに必要なのが
「ひとりの空白時間」
を意識的に確保することです。
- 予定を詰めすぎず、あえて“何もしない時間”を入れる
- カフェや公園など、安心できる場所でぼーっと過ごす
- スマホを見ずに五感を感じる時間を持つ(風や匂いなど)
- ノートに思ったことを書いて、頭の中を整理する
- 「ひとり時間=自分を回復させる時間」
私は仕事中、
頭がいっぱいになり
混乱気味になり
思考停止(フリーズ)しそうになる
ことがあります。
そんな時は、意識的にひとり時間
を作るようにしています🍀
安心できる場所で
目を閉じ
脱力し
ただただ深呼吸
脳に十分な酸素を送るイメージで
たとえ1分間だけでも休息の効果があると感じています🍀
フリーズしそうになったら、脳の再起動を🧠
まとめ
人と心地よい距離を保つためには、
「相手にどう思われるか」よりも
「自分がどう感じるか」
を大切にしましょう。
- マウンティングには冷静な距離感で対応する
- 相手を変えるより、自分の受け止め方を見直す
- 悪口や自慢話は“受け流す技術”を身につける
- クレームや上司の無茶振りには冷静に境界線を引く
- 部下への指導では「思いやり」と「芯」を両立する
- 心の余白を取り戻すために、ぼーっとする時間を大切にする
人間関係は「がんばるもの」ではなく、
「心地よくあるための工夫」が大切です。
自分のペースを尊重することで、
他人との関係も自然と楽になっていくと信じています🍀
【参考文献】
最後までお読みいただき、ありがとうございました✨
いつも、記事を読んでくださり本当にありがとうございます🍀
この記事を読まれた方が、
少しでも『人間関係を築くコツ』について興味を深めていただき、
少しでも参考になれば嬉しいです🌈
今後もできる限り有益な記事を書いていきますので
よろしくお願いします。
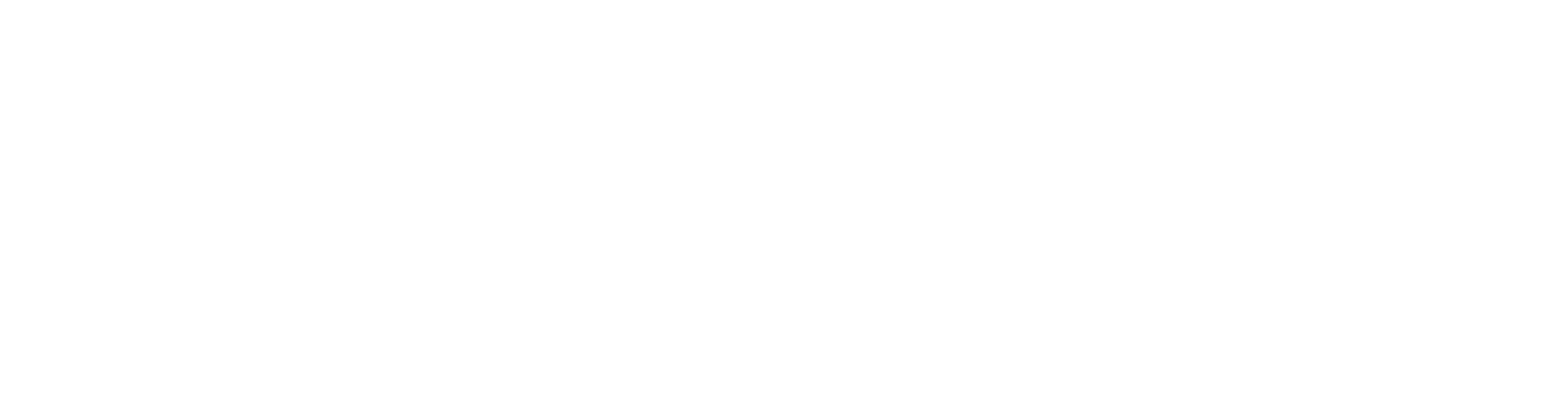



コメント