「この人、なんだか信頼できそう」
「今回はツイてないだけだ」
――そんな風に思ったことはありませんか?
実はそれ、思考をゆがめる
“認知バイアス”
かもしれません。
認知バイアスとは、
私たちの脳が素早く判断するために使っている近道(ヒューリスティック)のようなものです。
ただし、その「近道」はときに間違った結論を導くこともあります。
今回は、日常のさまざまなシーンに隠れている代表的なバイアスをいくつか紹介します。
私たちがどんな思い込みをしやすいのか…
以下の文献を参考にしながら、一緒に学んでいきましょう💪
【参考文献】
代表性ヒューリスティックとは?
~「見た目」で判断してしまう私たち~
たとえば職場で新しく入ってきた人が、スーツ姿で落ち着いた話し方をしていたとします。
「きっと仕事ができるタイプだ」
と思い込んでしまうのは、代表性ヒューリスティックの典型例です。
ほかにもこんな場面で…
- おしゃれなカフェ=おいしいに違いない
- 黒ずくめの男性=なんとなく怖い
- かわいいパッケージ=安全な商品
「それっぽい」
という見た目や印象に引っぱられて、事実を見落としてしまうことがあります😅
第一印象も大切ですが、そこにとらわれすぎず、じっくり観察することが重要ですね🍀
セルフ・サービング・バイアスとは?
~うまくいけば自分のおかげ、失敗すれば運のせい?~
仕事でプレゼンがうまくいったとき、
「私の準備が完璧だったからだ」
と思う一方、
うまくいかなかったときには
「時間が足りなかったからだ」
と考える……。
こうした自己評価の偏りがセルフ・サービング・バイアスです。
家庭や人間関係でも…
- 夕飯の味付けがうまくいけば「センスがいい」と思い、失敗すれば「調味料が変だった」
- 子どもが褒められたときは「自分の育て方がよかった」、叱られたときは「先生が厳しすぎる」
自信を守るための自然な心の働きですが、ときには客観的に見直すことも必要です。
フォルス・メモリーとは?
~記憶はあいまいで、書き換えられていく~
昔の家族旅行の話で、
「あのとき温泉入ったよね?」
と話したら、他の家族は
「そんな温泉なかったよ」と言う――。
こうした“思い違いの記憶”がフォルス・メモリーです。
身近なところでは…
- 小学生時代に先生にほめられたと思っていたら、実際は注意された記憶だった
- 友達と会話した内容を、他の誰かとのやり取りと勘違いしている
- SNSで見た情報を、あたかも自分の経験のように話してしまう
私たちの記憶は常に再構成されていて、「正しい記憶」だと思っているものでも、案外あてにならないことがあるのです。
現状維持バイアスとは?
~「変えるのが面倒」にひそむ心理~
スマホの料金プランが見直しで安くなると聞いても、
「今のままでいいか」
と思ってしまう。
これが現状維持バイアスです。
日常の例として…
- 定食メニューでいつも同じものを選んでしまう
- 通勤ルートを変えるのが面倒で、混んでいても同じ道を使う
- 職場の古いやり方を「変えるのが怖い」と思って続けてしまう
変化にはエネルギーが必要です。
でも「一歩踏み出すと楽になることもあるかも」と、少し視点を変えてみると選択肢が広がります。
プロスペクト理論とは?
~「得」より「損」を避けたい心理~
スーパーで
「あと2時間で値引き終了!」
と書かれていると、つい買ってしまう。
この「損したくない」気持ちがプロスペクト理論です。
こんなシーンにも…
- ポイントカードを忘れて損した気がしてしまう
- 通信プランの変更をためらうのは「今の特典を失いたくない」から
- 割引キャンペーン終了の案内で急いで契約してしまう
利益よりも損失の方が強く感じられるため、冷静さを失いがちになります。
「本当に必要かどうか」を一呼吸おいて考える習慣が役立ちます。
フレーミング効果とは?
~言い方ひとつで印象が変わる不思議~
病院で
「この手術は成功率90%です」
と言われると安心しますが、
同じ手術でも
「失敗する確率は10%です」
と言われると不安になります。
これは、同じ内容でも言い方によって印象が変わる「フレーミング効果」の影響です。
買い物でも…
- 「今なら30%オフ」と言われると得した気分
- 「元の価格に30%上乗せされていた」と聞くと損した気分
- 「無添加」と聞くと安心するけれど、具体的に何が無添加かは曖昧なまま
表現に振り回されず、事実をしっかり見る力が大切です。
まとめ(バイアスとの付き合い方)
~「思い込み」から一歩引く視点を持とう~
認知バイアスは、誰にでも起きる“思考のくせ”です。
私たちは毎日、数えきれない判断をしています。そのたびに、知らず知らずのうちに偏った見方をしているかもしれません。
でも、こんな工夫でバイアスを和らげられます!
- 自分の直感や判断に「本当にそうかな?」と問い直してみる
- 周囲の意見や違う立場からの視点を取り入れる
- 感情が強く出たときこそ、冷静に情報を見直してみる
認知バイアスは悪いものではありませんが、それに気づかず動かされ続けるのはもったいないことです。
Shall we 少しずつ「思い込みから自由になる練習」を ?
【参考文献】
最後までお読みいただき、ありがとうございました✨
いつも、記事を読んでくださり本当にありがとうございます🍀
この記事を読まれた方が、
少しでも『認知バイアス』について興味を深めていただき、
少しでも参考になれば嬉しいです🌈
今後もできる限り有益な記事を書いていきますので
よろしくお願いします。
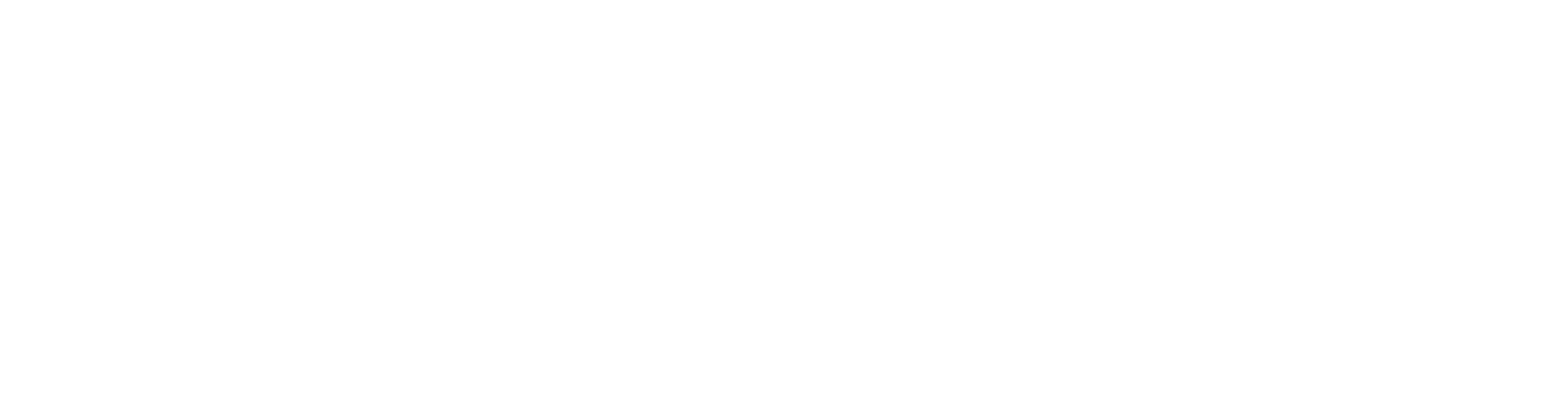



コメント