「服のタグがチクチクして着られない」
「シャンプーが苦手」
「教室の音が気になって集中できない」
子どものこんな様子を「わがまま」「甘え」と感じたことはありませんか?
実はその背景に、
「感覚処理障害(Sensory Processing Disorder:SPD)」
がある場合があります。
SPDとは、目・耳・鼻・口・皮ふ・体のバランスなどの感覚情報を、脳がうまく整理できないために生活に困りごとが出てしまう状態を指します。
SPDは大きく3つに分けられます。
- 感覚調整障害
- 感覚ベースの運動障害
- 感覚識別障害
今回は、感覚について一緒に深ぼっていきましょう💪
感覚調整障害とは?(過敏・過小・感覚探究)
感覚に対して「強すぎる反応」や「弱すぎる反応」があるタイプです。
例えば…
- 感覚過敏(敏感すぎる)
- 光がまぶしすぎる
- 音が大きく聞こえる
- 服のタグや靴下のゴムが気になる
- 歯磨きや爪切りを嫌がる
- 感覚過小反応(鈍感すぎる)
- 大きな音に気づかない
- 転んでも痛がらない
- 先生や友達に声をかけられても反応が遅い
- 感覚探究(刺激を求める)
- ぐるぐる回るのが大好き
- 強く押したり、ぶつかったりする遊びを好む
- 大声を出したり、体を激しく動かしたがる
子どもがどんな感覚を苦手としているのか
求めているのか、分析することで、手立ての工夫点が見えてきます🍀
感覚ベースの運動障害とは?(行為機能・姿勢調節)
体を思いどおりに動かすのが難しいタイプです。
- 行為機能の苦手さ(動作の計画が苦手)
- 靴ひもを結ぶのに時間がかかる
- ハサミで紙をうまく切れない
- ダンスや体操のまねが苦手
- 初めての動きの習得が難しい
- 姿勢調節の苦手さ(バランスが取りにくい)
- 椅子にじっと座っていられない
- すぐに転ぶ
- ジャンプやスキップが苦手
感覚識別障害とは?
感覚を正しく「見分ける」ことが難しいタイプです。
- 手探りで物を区別できない
- 音の方向や高さがわかりにくい
- 似た形の文字や物の違いがわかりにくい
その結果、「不器用」「要領が悪い」と誤解されやすくなります。
視覚
聴覚
触覚
味覚
嗅覚
前庭感覚(バランス感覚)
固有覚(体の深部感覚のことで、筋肉の力加減や、関節の曲がり具合を調整したりする)
感覚処理障害の具体例
日常の中でよく見られる様子を紹介します。
- 学校生活で
- チャイムやざわめきが気になって授業に集中できない
- 体育でボール遊びや縄跳びが苦手
- 給食で特定の食感や味を嫌がる
- 家庭生活で
- 洋服の素材やタグを嫌がる
- シャンプーや歯磨きを怖がる
- 食べられるものが限られている
- 遊びや友達関係で
- 激しい遊びを求め続ける
- 逆に、ちょっとした刺激で泣きやまない
- 友達と同じ遊びが苦手で孤立することがある
家庭でできる工夫 🏠
環境を整える
- 洋服のタグやチクチク素材を避ける
- 靴下や下着は子どもが心地よい素材を選ぶ
- シャンプーのときにシャワーの水圧を弱める/タオルで拭く工夫をする
- 歯磨きは毛先の柔らかい歯ブラシを選ぶ
- 食事は「食べられるもの」から広げていく(無理に食べさせない)
- 家の中で静かに過ごせるスペースをつくる
感覚あそびを取り入れる
- ブランコ・トランポリン・バランスボールで体を動かす
- 粘土や砂遊びなど「手で感じる遊び」を取り入れる
- お布団やクッションで「ぎゅっと抱きしめられる感覚」を味わう
- ボール投げやキャッチ遊びで手と体の感覚を育てる
生活リズムを工夫する
- 予定や順番をイラストやカードで見える化する
- 外出前に「これから何をするのか」を伝える
- 学校から帰ったら「休む→宿題→遊ぶ」など一定の流れを決める
学校でできる工夫 🏫
環境調整
- 教室の蛍光灯の明るさを調整する/座席を後方や窓際にする
- イヤーマフや耳栓を使えるようにする
- 黙々と作業できるスペースを用意する
- 体育では前もって内容を説明して安心させる
学習のサポート
- 板書やプリントを見やすい位置に配置する
- 課題は細かいステップに分けて提示する
- 筆記や工作で不器用さが出るときは、道具を工夫(太めの鉛筆、持ちやすいハサミなど)
- 集中しやすい短い時間で区切りをつける
友達関係のサポート
- グループ活動のときに安心できる友達と組ませる
- 無理にみんなと同じ遊びをさせず、好きな遊びを選ばせる
- 感覚探究の行動(走る・回る)を安全にできる場を確保する
教師・周囲の理解
- 「わざとやっているのではなく、感じ方のちがい」と理解する
- 困っているときは「何が嫌なのか」「どうしたいのか」を聞く
- 成功体験を積ませて「できた!」を大切にする
いきなり全てを実行する
というよりは、支援者の負担的にも
取り組みやすい内容から
お子さんにあった支援を探っていくのが良いと考えています
少しでも参考になれば嬉しいです✨
感覚処理障害のアセスメントに用いられる標準化された検査
感覚処理障害(SPD)の理解や支援の第一歩は、正確なアセスメントです。ここでは、日本で臨床的に活用されることの多い代表的な標準化検査をご紹介します。
1. 感覚プロファイル(Sensory Profile)
- 対象年齢:乳幼児〜成人まで、バリエーションあり
- 方法:保護者や本人による質問紙形式
- 特徴:
- 感覚に対する反応を「過敏」「低反応」「感覚探究」などの観点から整理
- 日常生活の中での感覚反応の傾向がわかる
- 活用例:
- 子どもの「音に敏感」「体をよく動かしたがる」などの行動を体系的に理解
- 療育や学校での支援方法の参考にできる
2. 日本感覚イベントリー(Japanese Sensory Inventory, JSI)
- 対象年齢:主に乳幼児〜学童期
- 方法:保護者記入式の質問紙
- 特徴:
- 日本の文化や生活習慣に合わせて開発された尺度
- 感覚処理の困難さを「過敏」「過小反応」「感覚探究」といった側面で測定
- 行動観察や臨床面接とあわせて活用することで、子どもの感覚特性をより具体的に把握できる
- 活用例:
- 幼稚園・保育園・学校での集団生活への適応の難しさを理解
- 感覚統合療法や環境調整の必要性を検討する材料になる
3. 感覚統合と運動計画検査(Sensory Integration and Praxis Tests:SIPT)
- 対象年齢:4歳〜8歳11か月
- 方法:臨床家が直接子どもに課題を実施(描画、動作、手先作業など)
- 特徴:
- 感覚入力と運動計画(プランニング)の力を多角的に評価
- 実施には専門的な研修を受けた評価者が必要
- 活用例:
- 「不器用さ」や「運動のぎこちなさ」の背景にある感覚処理の特性を明らかにする
- 個別療育や作業療法プログラムの立案に役立つ
まとめ
感覚処理障害(SPD)は、子どもの「性格の問題」や「わがまま」ではなく、
感じ方のちがい
によるものです。
- 感覚調整障害(過敏・過小・探究)
- 感覚ベースの運動障害(行為・姿勢)
- 感覚識別障害
大きく3つのタイプがあります。
子どもは「困らせたくて」行動しているわけではありません。
「どう感じているのかな?」と視点を変えることで、子どもへの理解がぐっと深まります。
支援や工夫しだいで、子どもは安心して自分の力を発揮できるようになります。
感覚処理障害を知ることで
子どもの「その子らしさ」を尊重し、笑顔で過ごせる毎日につながると信じています🍀
最後までお読みいただき、ありがとうございました✨
いつも、記事を読んでくださり本当にありがとうございます。
スキ・フォローとても励みになっています🍀
この記事を読まれた方が、
少しでも『感覚処理障害(SPD)』について興味を深めていただき、
少しでも参考になれば嬉しいです🌈
今後もできる限り有益な記事を書いていきますので
よろしくお願いします。
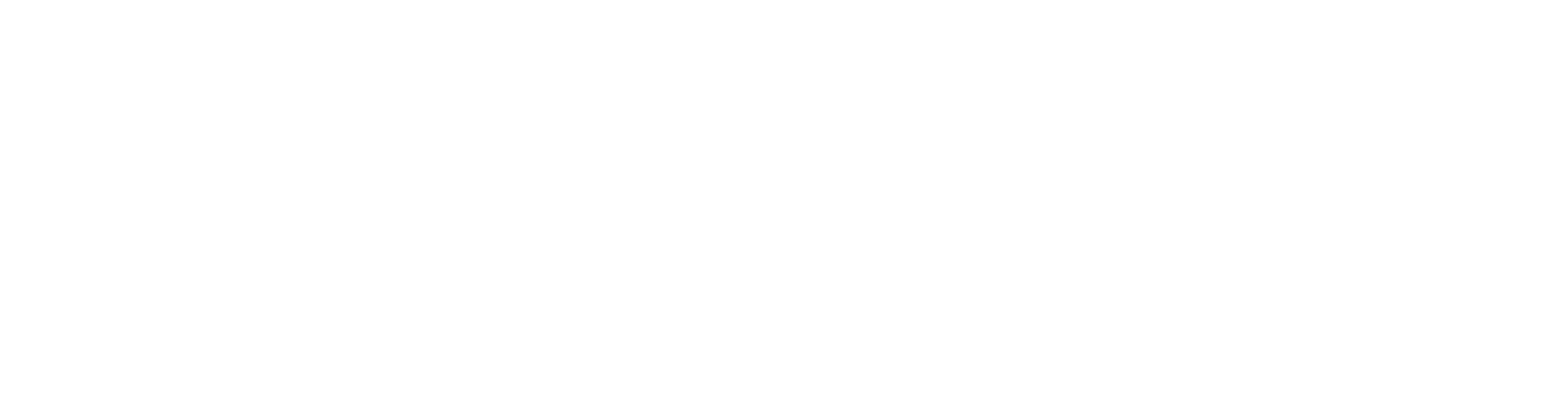



コメント