リーダーらしい話し方とは
『リーダー』
と聞くと、どんな人をイメージしますか?
優秀なリーダーは、ただ指示を出す人ではありません。
人の注目を集めて
思いを伝えて
一緒に進んでいく人のことだと考えています。
だからこそ
「何を言うか」以上に
「どう話すか」が大事になります。
大切なのは、話し方にちょっとしたコツを加えてみること
カギになるのが「セルフ・パペット」という考え方です。
これは、難しいテクニックではなく、誰でも今日から使えます。
自分の中のいろんな「自分」を使い分けてみる
以下の文献を参考に一緒に学んでいきましょう。
【参考文献】
セルフ・パペットとは
セルフ・パペットというのは、簡単に言えば
「自分の中の役割を操る」
ことです。
『素の自分』と切り分けた
『リーダーとしての自分』
場面にあわせて自分を俯瞰的見て、『リーダーとしての自分』
操り人形のように自分を操るイメージです。
たとえば、こんな役割を持っている人は多いはずです。
- はっきり物を言うリーダー役
- 和ませ役のムードメーカー
- 静かに寄り添う聞き役
- データを示す専門家役
- 気持ちに共感するサポーター役
これをうまく切り替えると、話に引き込まれやすくなります。
難しそうに見えて、ちょっと意識するだけで誰でもできます。
セルフ・パペットを使えると、こんな良いことがあります。
- 話を聞いてもらいやすくなる
- 相手の心に届きやすくなる
- 信頼してもらいやすくなる
- チームに「基準」を示せる
- 「この人についていきたい」と思われる
影響力をもつ話し方: 注目を集める
話を聞いてもらうには、まず「え、なに?」と耳を向けてもらわないといけません。
そのために大事なのが、最初のつかみです。
ここでもセルフ・パペットの出番です。
たとえば、こんな始め方があります。
- ちょっと意外なデータをサラッと伝える専門家役
- 「さっきこんなことがあってね」と雑談を混ぜるフレンドリー役
- 静かに「大事な話があります」と落ち着いた声で話す落ち着き役
声のトーン、間の取り方、目線の配り方で印象はぐっと変わります。
また、登場までの時間に、注目を集める工夫(落ち着いた一定のリズムの足音)
敢えて”コツッコツッ”と音のなりやすい靴を履いているリーダーをたくさんいます。
一度意識して試してみてください。
「あれ、なんだか聞いてくれるな」と感じることが、きっとあるでしょう🍀
高揚感を高める
人は「面白い!」「やってみたい!」とワクワクしたときに動きます。
だから、話す側がまず熱をもっていることが大事です。
熱を伝えるには、自分の中の「情熱パペット」を前面に出しましょう。
たとえば、
- 声をちょっと大きめにして、身振りをつけて話す
- 「私はこれを絶対にやりたいと思っています」と言い切る
- 小さな成功を一緒に喜ぶ共感役にスイッチする
聞いている人は、話し手の温度に引っ張られます。
ワクワクしたいなら、まず自分がワクワクすることが近道です。
信頼感を与える
いくら話し方が上手でも、「この人、信用できないな」と思われたら意味がありません。
信頼してもらうには、言葉の一つひとつに誠実さが必要です。
ここで使いたいのが、誠実な「共感役」と冷静な「説明役」です。
ポイントは、
- 嘘はつかない
- わからないことは「わかりません」と言う
- データや根拠を示して話す
- 相手の気持ちにちゃんと耳を傾ける
「この人はちゃんと向き合ってくれる」と思ってもらえることが、信頼につながります。
基準を示す
リーダーが大事にしている考えを言葉にして伝えること。
これが「基準を示す」ということです。
たとえば、
- 「うちのクラスでは挑戦することを大事にします」
- 「正直でいることが一番です」
- 「失敗してもいい、学ぶ姿勢が大事です」
言葉にして伝えると、相手は「どう行動すればいいか」がわかります。
ただし、自分がその基準を守っていないと説得力はゼロです。
だからこそ、まずは自分が示すことが大事です。
器の大きさを見せる
最後に大切なのが、「この人ならついていきたい」と思ってもらえる器の大きさです。
器の大きさとは、余裕や寛容さです。
ここで出番なのが「受け止め役」や「哲学者役」です。
たとえば、
- 意見を頭ごなしに否定しない
- 反対意見にも「そういう考えもあるね」と受け止める
- 「過去の失敗も今の自分には大事だった」と話す
話し方のテンポをゆっくりにするだけでも、余裕が伝わります。
焦らず、堂々と話すだけで、周りは安心してついてきます。
教壇に立つリーダーとして教員に求められる話し方
教員は、子どもたちにとって身近なリーダーです。
だからこそ、セルフ・パペットの活用は授業や学級経営にぴったりです。
たとえば、
- 難しい話をわかりやすくする「わかりやすい先生役」
- 子どもに寄り添う「聞き役先生」
- ユーモアで場を和ませる「楽しい先生」
- 時には厳しくルールを伝える「指導者先生」
- 「君はどう思う?」と問いを投げかける「問いかけ役」
授業で注目を集めたいときは、声の抑揚や板書、アイコンタクトを工夫してみてください。
「面白そう!」と思わせる一言があるだけで、子どもの目は輝きます。
信頼してもらうには、子どもの声にちゃんと耳を傾けることが一番です。
そして、「このクラスでは何が大事か」という基準を言葉にして、みんなで共有してください。
最後に大事なのは、失敗しても受け止めてくれる器の大きさです。
「大丈夫、失敗は成長の種だよ」と言える先生の言葉は、子どもの心にずっと残ります。
最後に
リーダーとしての話し方は、特別な才能ではありません。
ちょっとしたコツと、自分の中の「セルフ・パペット」を知っておくだけで、誰でもできます。
教員こそ、この技を一番生かせる仕事の一つです。
子どもの心に届く話し方を、一緒に育てていきましょう。
【参考文献】
最後までお読みいただき、ありがとうございました✨
いつも、記事を読んでくださり本当にありがとうございます🍀
この記事を読まれた方が、
少しでも『リーダーの話し方』について興味を深めていただき、
少しでも参考になれば嬉しいです🌈
今後もできる限り有益な記事を書いていきますので
よろしくお願いします。
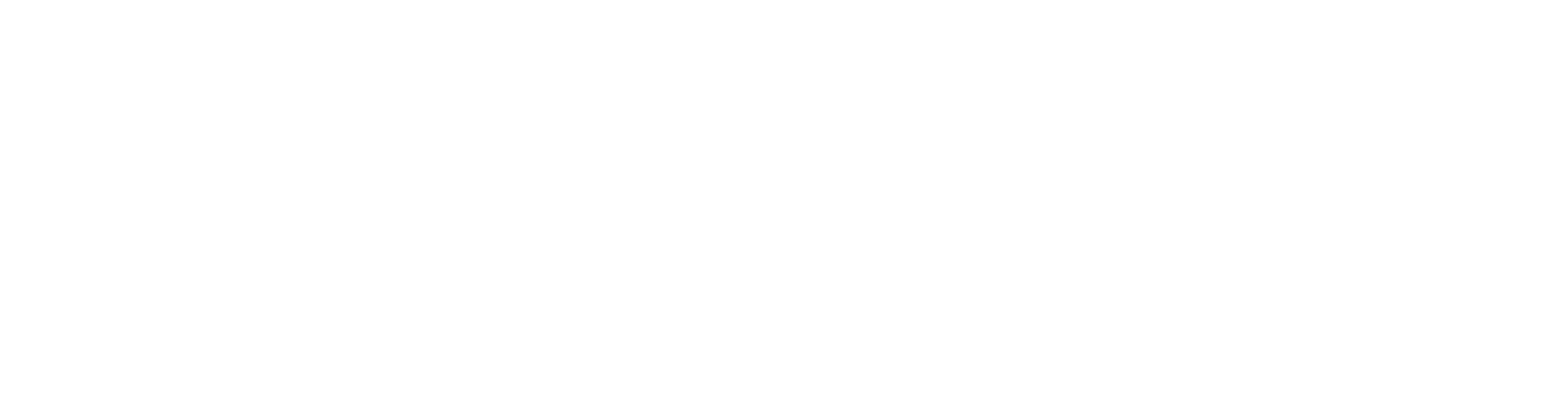



コメント