『性教育』
と聞くと、思春期ごろから始めたらいいかな?
と感じる方も、多いのではないでしょうか。
特に日本では諸外国と比べて、性教育についての大人の抵抗感が強く
知識不足のまま思春期に入っている子が多いように感じます。
今回の記事では、以下の文献を参考に、
諸外国でどのような性教育がされているのか、
幼児期から始められる包括的性教育とはどんな内容かについて
一緒に学んでいきましょう✏️
🔍参考文献
- ユネスコ「国際セクシュアリティ教育ガイダンス(ITSE)」:
https://sexology.life/data/5-8years.pdf - UNESCO, UNFPA 他(2018)『International Technical Guidance on Sexuality Education』
◆包括的性教育(CSE)とは?
包括的性教育(Comprehensive Sexuality Education:CSE)とは、次のような内容を含む、発達に応じた教育です。
- 身体や心の発達に関する正しい知識
- 人間関係の築き方と感情の扱い方
- 性的自己決定権や人権への理解
- 性とジェンダーの多様性の尊重
- 健康と安全の保持に関するスキル
上記の内容は、思春期や成人期に突然教えるものではなく、
幼児期から段階的に伝えていくことが重要とされています。
子どもたちが将来、
自分自身を大切にし、
他者と健全な関係を築くための
「生きる力」の土台を育む教育です。
◆ITSEとは? 国際的な性教育ガイドライン
ITSE(International Technical Guidance on Sexuality Education)は、ユネスコ・国連人口基金などが策定した教育ガイドラインです。
- 科学的根拠に基づく内容がまとめられている
- 0歳〜18歳までの年齢区分に応じた段階的な学習内容
- 文化的多様性やジェンダー平等、人権を尊重する立場から構成
ITSEはすでに世界の多くの国や地域で取り入れられており、子どもの人権と健康を守る上で、信頼性の高い教材となっています。
このガイドラインにより、「何を」「いつ」「どのように」教えるかが明確に整理されています。
◆幼児期からの性教育がなぜ必要?
「性教育は思春期からでよいのでは?」と考える方も多いかもしれません。
しかし、ITSEでは幼児期こそ性教育の土台を築く最も重要な時期と位置づけています。
幼児期に性教育が必要な理由
- 自分の体を正しく知ることで、自尊感情が育つ
- 「ノー」と言える力が、性被害の予防につながる
- 他者との健全な関係を築く土台ができる
- 多様性を認める視点が、いじめや差別の予防になる
- 日常の中で自然に学ぶことで、性に対する前向きな意識が育まれる
つまり、性教育は「性についての知識」だけでなく、
人間としての健全な成長を支える教育なのです。
◆5〜8歳で学ぶ内容(ITSEによる指針)
5〜8歳は、小学校低学年期にあたる時期で、心身ともに多くの変化が始まります。
この時期に学ぶべき内容は、以下の6つの分野に分かれています。
① 人間の身体と発達
- 正しい身体の名称(例:陰部・胸・口・手など)を知る
- 身体の変化や機能についての基本的な理解
- プライベートゾーンの概念とその大切さ
- 「触れてよい場所/いけない場所」を知る
👉 自分の身体を知ることは、性被害の予防にも直結します。
② 人間関係
- 家族、友人、教師との関係性と役割
- 親密さや信頼、友情の意味
- 他者の気持ちに共感する力(思いやり)
- 相手との距離感、断る力(NOと言う力)
👉 良好な人間関係の築き方は、すべての人間関係の基礎です。
③ 価値観・権利・文化
- 自分の価値を認める(自尊感情)
- 家庭や文化によって異なる価値観の理解
- 子どもにも「意見を言う権利」「身体を守る権利」があること
- 人権・平等・尊重の基本的な概念を知る
👉 子ども自身の「小さな権利意識」を育てることが大切です。
④ 性とジェンダー
- 男女の身体的な違いと共通点
- 「男の子らしさ」「女の子らしさ」にとらわれない見方
- 性別に関する多様性(ジェンダーアイデンティティなど)
- 差別や偏見についての初歩的理解
👉 多様性を尊重する心は、いじめや排除を防ぐ土台になります。
⑤ 健康と幸福
- 自分の感情を認識し、表現する練習
- 怒りや悲しみ、不安とどう向き合うか
- 基本的な生活習慣(食事・運動・睡眠など)
- 精神的な健康への配慮
👉 身体と心の両面から、健康的な成長を支えることが性教育の役割です。
⑥ 暴力と安全
- 「いやなことはいや」と言っていいことを知る
- 信頼できる大人に相談する練習
- 知らない人との関わり方(実生活・オンライン両方)
- メディアやSNSでの安全な行動についての基本知識
👉 予防的な性教育は、子どもを危険から守る「盾」になります。
◆伝え方の工夫と大人の役割
幼児に伝えるときのポイント
- 日常の中で自然に話す(お風呂・着替え・絵本など)
- 難しい言葉ではなく、子どもが知っている語彙で話す
- 絵やイラストを使って視覚的に説明する
- 恥ずかしがらず、明るく・肯定的に話す
- 質問には「正しく・端的に・ごまかさず」答える
👉 子どもが「性について話していいんだ」と感じられる環境づくりが大切です。
◆世界の取り組みと日本の課題
- スウェーデン・オランダ・ドイツなどでは幼児期から性教育が義務化
- 性的虐待や妊娠の減少、ジェンダー平等の促進に成功
- 一方、日本では「性教育は慎重に」という空気が根強く、実践は限定的
👉 子どもの権利と成長のため、日本でも国際基準に沿ったCSEの導入が求められています。
◆性教育は「命を大切にする学び」
包括的性教育は、単なる性の知識ではなく、
- 「自分を守る力」
- 「人とつながる力」
- 「多様性を受け入れる力」
を育てる、命を尊ぶ教育です。
ITSEは、そのための信頼できる「道しるべ」です。
私たち大人がまず正しく学び、
子どもと向き合う準備をすることが大切だと考えています
🔍参考文献
- ユネスコ「国際セクシュアリティ教育ガイダンス(ITSE)」:
https://sexology.life/data/5-8years.pdf - UNESCO, UNFPA 他(2018)『International Technical Guidance on Sexuality Education』
最後までお読みいただき、ありがとうございました✨
いつも、記事を読んでくださり本当にありがとうございます🍀
この記事を読まれた方が、
少しでも『性教育』について興味を深めていただき、
少しでも参考になれば嬉しいです🌈
今後もできる限り有益な記事を書いていきますので
よろしくお願いします。
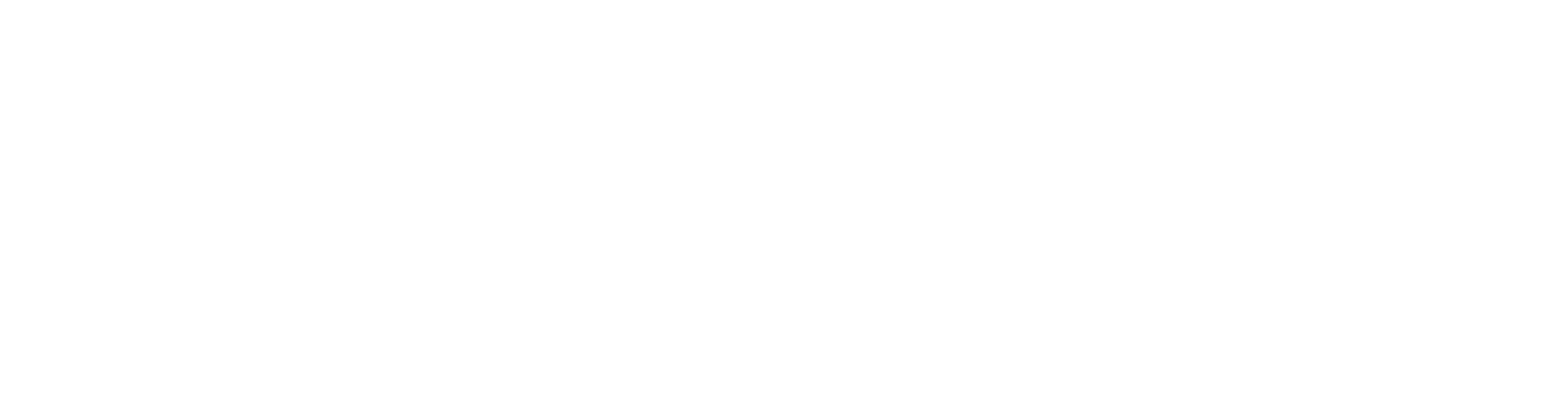



コメント